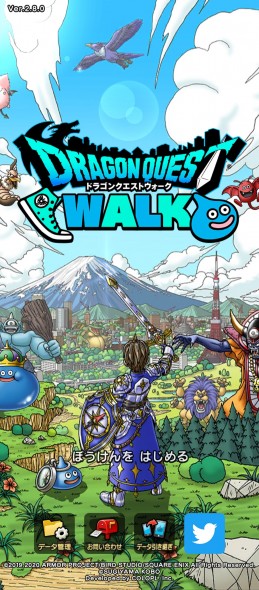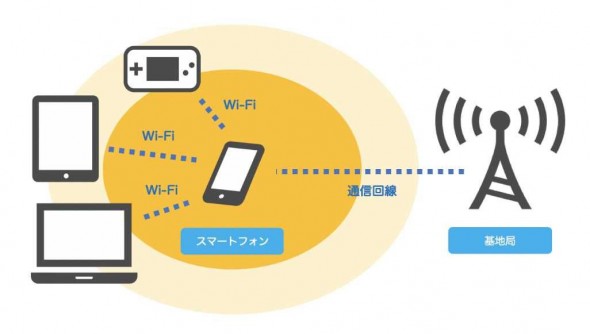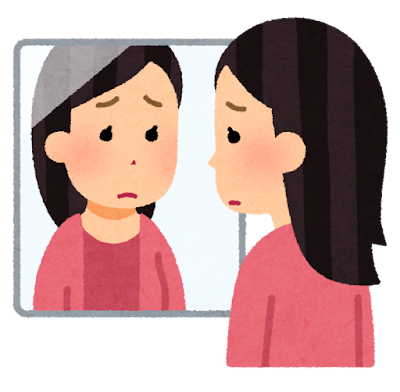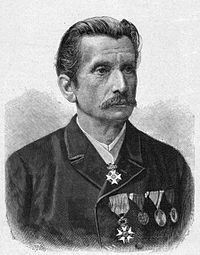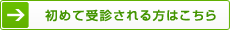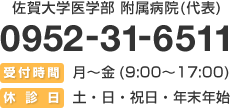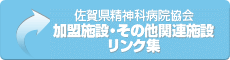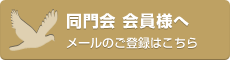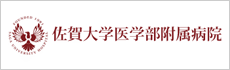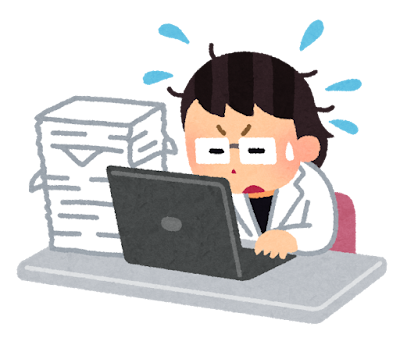
12月23日の日記で「精神保健指定医」について解説し、専門医についてもちょっとだけ触れましたが、もう少し詳しく解説します。研修医の先生向け。
…と言いつつ、詳細な応募資格・要件については学会登録メンバーでないと読めなかった。あんまり大っぴらに公開しちゃダメなのかもしれない。ので、恐縮ですが簡易な紹介にとどめておきます。

申請条件
・一定の期間(●●年)以上、研修を受けた
・認定を受けた施設で研修を受けた
・指導医(”指導医”の資格をもつ偉い先生)から指導を受けた
・一定の症例数を経験した
ちなみに受付は毎年1回だけ。間に合わなかったら仕方ない、来年まで待とう。
精神科に限らず、内科や外科の専門医でも、たぶん同じような条件だと思われる。
大学病院の医局に所属している若手の医師であれば、きちんと認定施設や指導医を割り当てられるため、さほど心配しなくて良い。ただ、医局に所属しないフリーの医師は、自分でしっかり下調べする必要がある。
ただし経験症例については要注意。精神保健指定医とは条件が異なります。特定の疾患だけでなく「精神科救急」「地域医療」「リエゾン」といった治療場面の条件があり、入院だけでなく外来診療の経験も必要になります。

申請
条件を満たしたら、学会へ書類を提出し、受験を申し込む。
まずは提出した書類を審査される。この時点で「レポートの内容が不十分!」と不合格になる場合がある。
無事にパスしたら、受験票が送られてくる。

筆記試験
全国複数個所に試験会場が設けられます。
どんな問題か、どんな対策が必要かについては後で解説。

面接試験
筆記試験をパスしたら、最後に面接。「どうして専門医になりたいと思ったのですか」という質問に対し「以前から興味がありまして」…なんて内容ではない。「経験した症例、〇〇病と診断した根拠は?」「どうしてこの治療法を選んだ?」「例えば患者さんが……と言った場合、あなたはどう答える?」という具合に、専門家としての知識、判断能力、コミュニケーション能力について厳しく評価される。
(ちなみに受験手引書に「※コミュニケーション能力には、表情・態度・会話の内容の他に声の大きさも評価されます。」って大文字で書いてありました。)

認定証交付
無事に合格した先生、おめでとうございます!これで今日から立派な専門医!
…の前に最後の手続き。交付のための料金(●万円)を支払う必要があります。お忘れなく。

合格率
第1回(2009年)から第11回(2019年)まで、受験する人は増加傾向。
直近では毎年、500人前後が受験している。
…で、合格率は だいたい6~7割程度のようです。
試験対策

新興医学出版社 日本精神神経学会 専門医認定試験問題 解答と解説 第1集〔第1回~第3回〕
ISBN:9784880028583

新興医学出版社 日本精神神経学会専門医認定試験問題 解答と解説 第2集〔第4回~第6回〕
ISBN:9784880028613
過去問が出版されていますので、まずはこれを解きながら勉強していきましょう。(私も現在、勉強中。)
ちなみに問題は難しいというよりも、幅広い、という印象。医師国家試験に出てくるレベル(教科書に載っている範囲内)もあるけれど、最新の論文を読んでないと解けないような激ムズ問題まである。「わしゃ10年以上も精神科医を勤めてきたんじゃ!」…と経験豊富な先生であっても全く安心できない。経験したことがない珍しい疾患や治療法であっても容赦無く知識を問われるため、それなりに対策をたて、試験勉強しなければならない。大変です。
まとめ
専門医への道は険しい…けど学会側としては「たくさん勉強して、早く一人前になってくれ!」という想いがあるようです。(学会のメンバー向けサイト内に「専門医を目指す方向けテキストのご案内」という親切なページがある。)
偉い先生たちの優しさ、指導に感謝しつつ、日々勉強に励んでいきましょう。
以上。




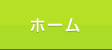
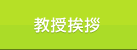
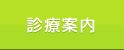


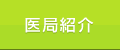
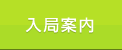



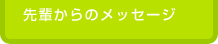
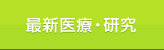




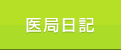
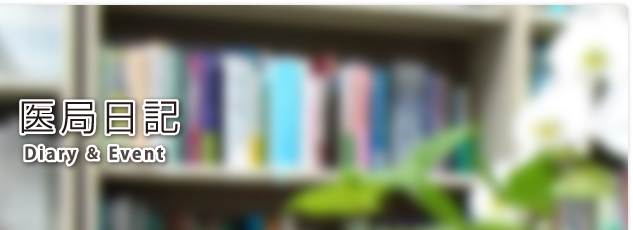
 (
(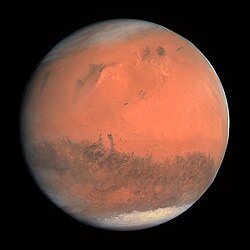 (
(

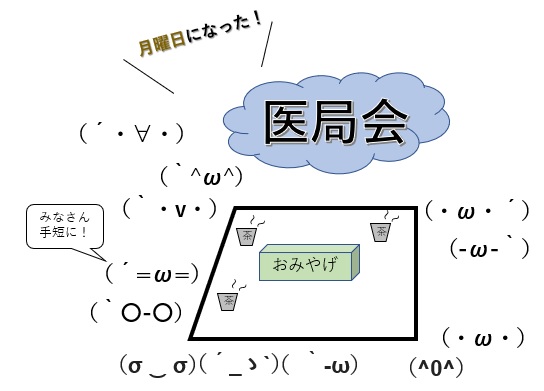
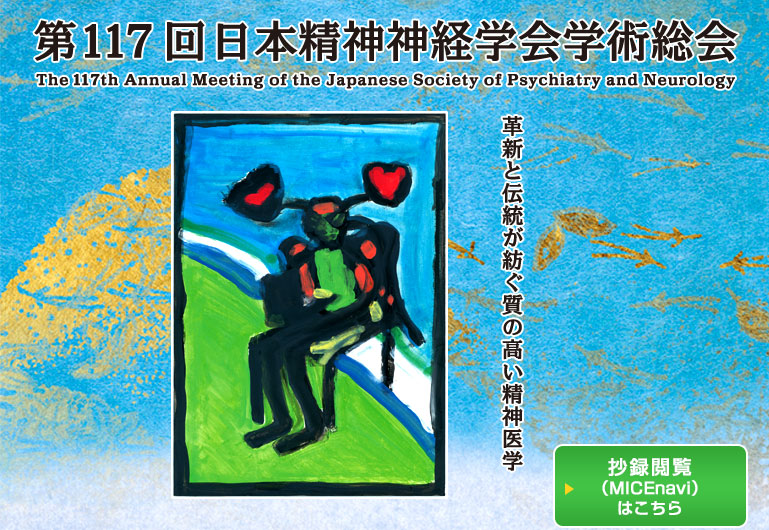
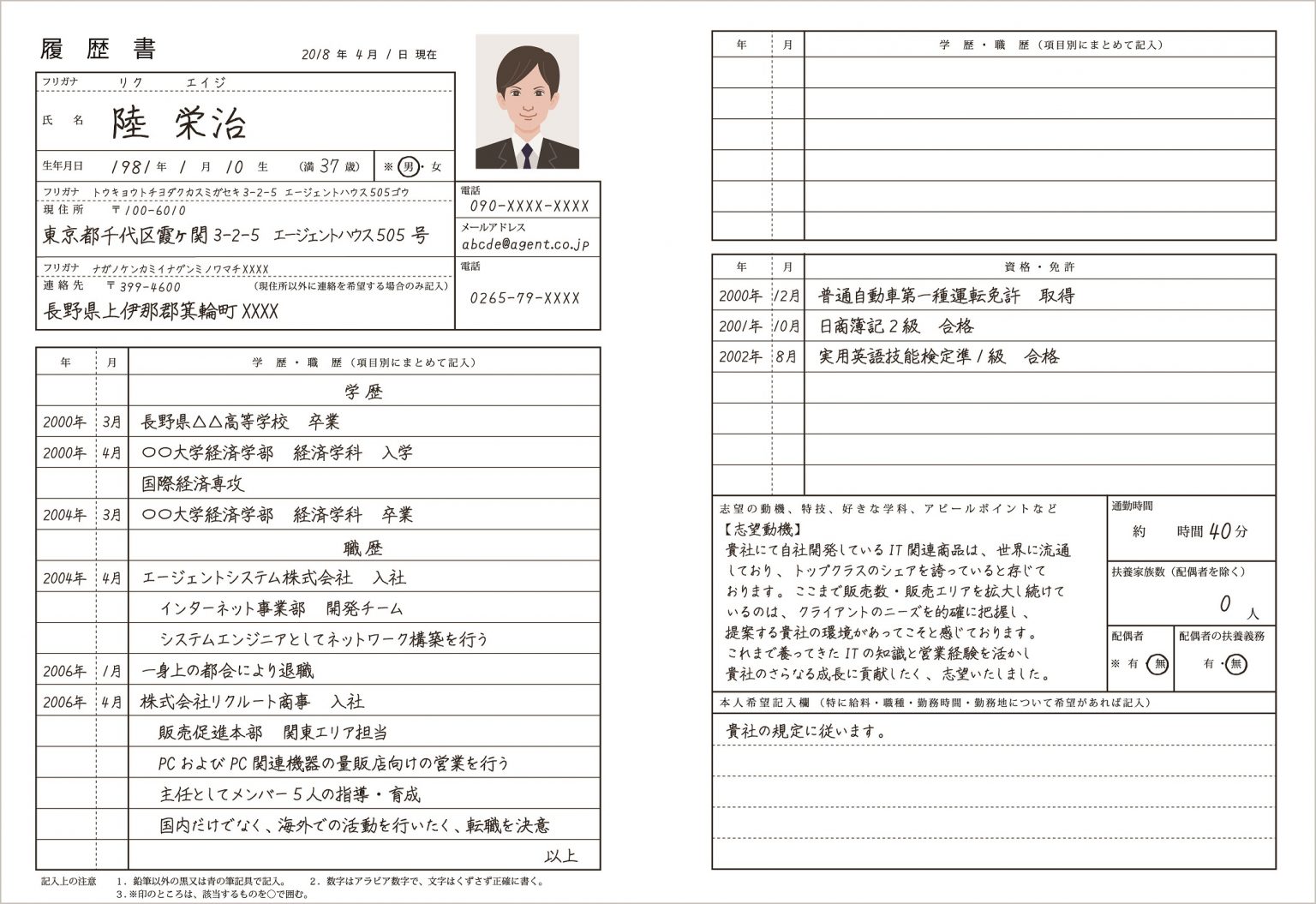




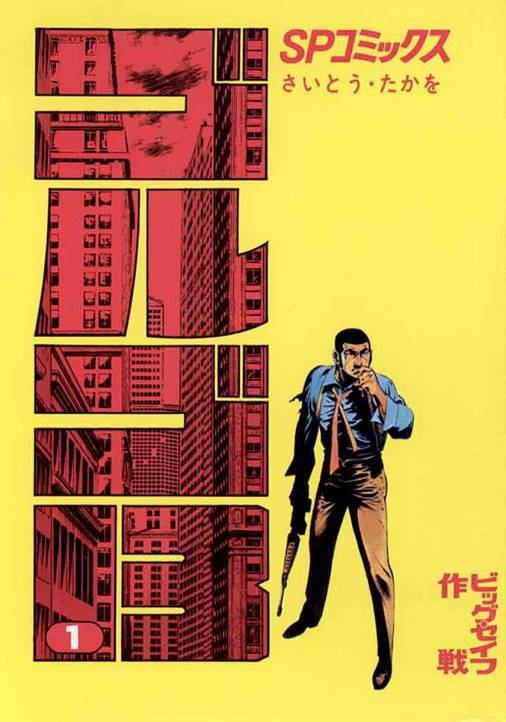
 (
(