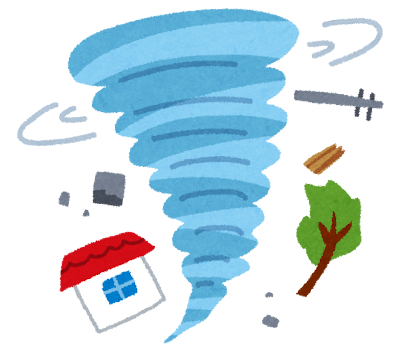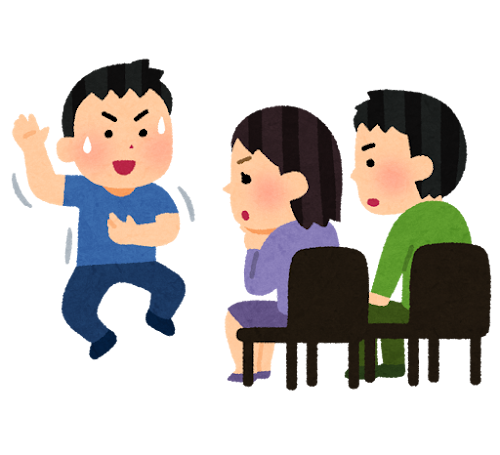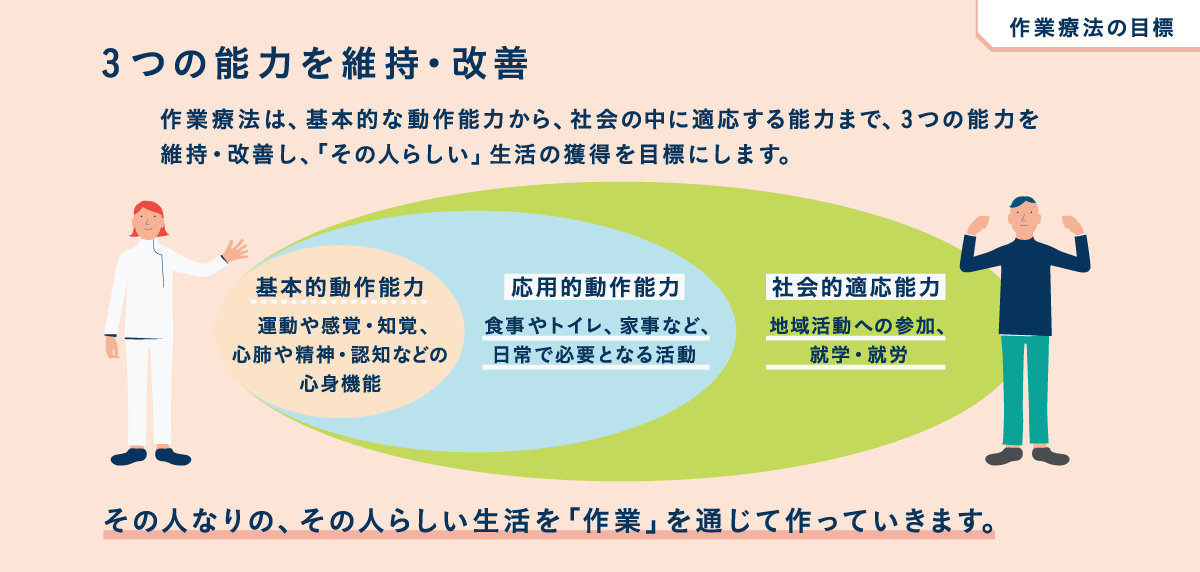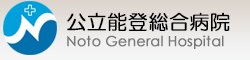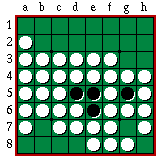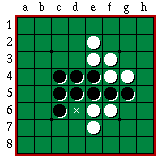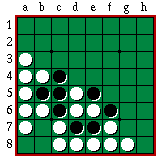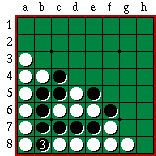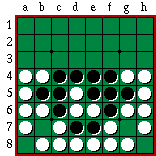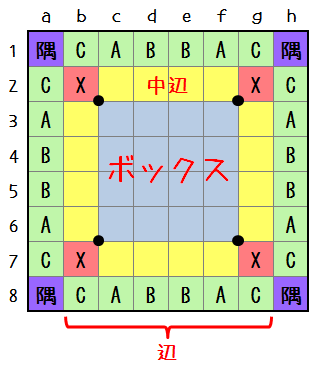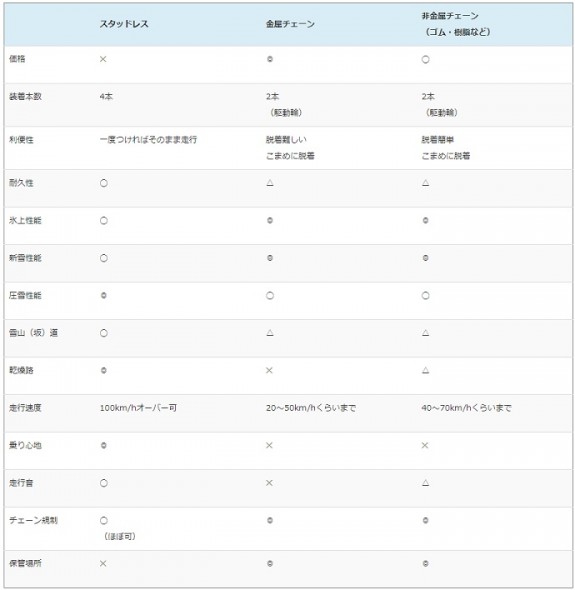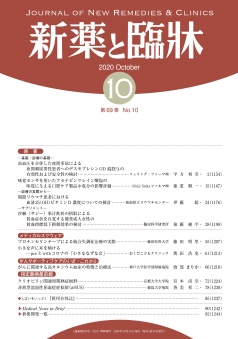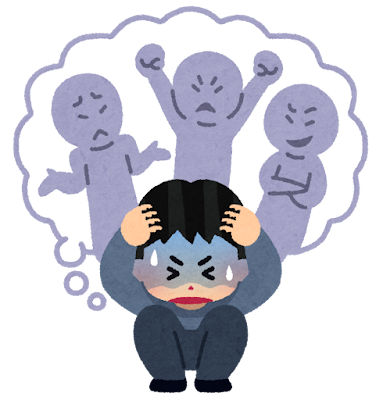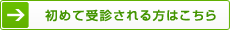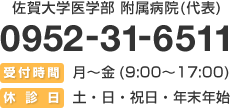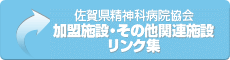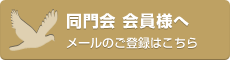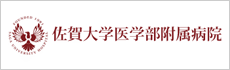すれ違い、悲劇的な結末を迎えた二つの愛。シェイクスピアの演劇的仕掛けまでも訳出した『新訳 オセロー』
一六二三年のフォーリオに収められた本作の題名も『ヴェニスのムーア人オセローの悲劇』であるから、これが本作の正式な題名と言えよう。
なぜオセローは最愛の妻を殺してしまったのか。なぜイアーゴーの正直さ(honesty)を信じ、妻の貞淑さ(honesty)を疑ったのか。オセローにイアーゴーを疑うという発想がなかったのは、部下を大事に思う上官としては自然なことであり、ましてや「正直なイアーゴー」という評判がある部下ならなおさらだった。だからといって、部下を信頼したがゆえに最愛の妻を疑ったという単純な話でもない。ヴェニス一の美女から愛されているという思いは、彼の男性性を支える大きな基盤となっており、だからこそ、自分に自信があるあいだは、妻の愛を疑うことなどなかった。その絶対的な自信が崩れたとき、自分は本当に妻に愛されているのかと疑い始めるのである。
オセロ症候群

telling, それってほんとに愛情表現? いき過ぎた束縛、もしかしたら「オセロ症候群」かも 2020/02/07
恋愛関係にあるパートナーに対して、誰よりも自分を大切にしてほしい、他の異性とあまり親しくしないでほしい、と思うのはとても自然なこと。しかし、その思いが相手への “過剰な束縛” に繋がってしまうのなら話はまた別。それ、もしかしたら「オセロ症候群」の症状かもしれませんよ。 精神科医・木村好珠先生に、「オセロ症候群」の症状や兆候の見分け方、そして対処法までじっくり教えていただきました。
「オセロ症候群」は、シェイクスピアの四大悲劇の一つ「オセロー」で、妻に激しい嫉妬の念を抱く主人公の名前から命名されました。一般的な症状としては、お付き合いしているパートナーや結婚相手に対して、たとえば「勝手にスマホを覗く」「メールを見る」など、過度な束縛行為をしてしまうことが挙げられます。
「オセロ症候群」の可能性が疑われる行動としては、このような例があります。
・スマホを勝手に覗く
・相手のSNSを執拗にチェックする
・1日に何回も電話をかける
・1日に何十回もメールを送る
・すぐに電話の折り返しやメールの返信がこないと不安になって相手にあたる
・「仕事に行ってほしくない」など、日常の行動まで制限する言動
・スマホにGPSをつける
また、こうした束縛をしても、決して安心感を得られないというのも特徴です。オセロ症候群にかかってしまう人たちに共通していると言えるのは「自己肯定感が低い」ということ。誰かに見捨てられてしまうという不安が、相手を束縛するという行為に繋がってしまうんです。ただ、本人の中では束縛していることをあまりマイナスにとらえておらず、自覚症状がない場合が多いのが実情。あくまでも、相手に対する愛情表現だと思っているんです。だからこそ理解が得られないと「なんでわかってくれないの?」「不安にさせているのはあなたでしょ?」と、あくまでも被害者側の意識になってしまう。

オセロ症候群とは|診断チェックや心理状況、治療の必要性について 更新日 2018年07月20日
「オセロ症候群」のような強い嫉妬妄想は、以下のようなパーソナリティ障害や病気に起因していることもあります。
妄想性パーソナリティ障害
アルコール依存症
妄想性障害
これらの場合、速やかに専門医の適切な治療を受けることが必要です。またそれ以外の場合でも、過去の経験による大きな認知の歪みの是正、親との向き合い等、嫉妬妄想は根本にある部分の対処をすることが重要になります。自分自身だけで嫉妬を抑えきれない場合、早めにカウンセラーに相談をしてみましょう。
【おまけ】オセロ(リバーシ)入門

精神科の病棟、デイケア棟では大抵、レクリエーション用としてオセロが置いてある。
ルールが分かりやすいので誰でも気軽に楽しめる。…と見せかけて実は結構奥が深いゲーム。
というわけで解説。
オセロ or リバーシ

どこが違う?「オセロ」と「リバーシ」の違い 2020年5月12日
1883年 リバーシ誕生。英国ウォーターマン氏、モレット氏が考案。
1973年 オセロ誕生。日本の長谷川五郎氏が考案。ツクダ社による商標登録。
1993年 オセロの意匠権(ゲームの形式に関する権利)が失効。以後、リバーシの名で類似品・ソフトが流行。
1883年のリバーシの時点で現在のルールとほぼ同じ。長谷川氏によると、オセロは囲碁をヒントに、シェイクスピアのオセロ(さまざまな登場人物が寝返るというストーリー展開)のイメージで発案したとの主張。パクリなのか偶然なのかは不明。ひとまず「オセロ」はツクダ社の商品名ということになりますので、「リバーシ」の名で呼んでおけば通っぽく振舞えるでしょう。たぶん。
オセロの基本戦術
とりあえず序盤~中盤にかけての基本戦術を紹介。これ知ってるだけで全然違う。

https://www.othello.org/ より
・少なく取る
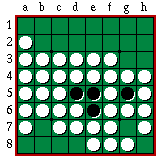
多くの初心者が持ってしまう誤解があります。それは「とにかく石が多い方が有利」と思ってしまうことです。実際はそれとは逆で「石の多いほうが不利」「石の少ない方が有利」である場合がほとんどです。そのわけは打てる箇所数にあります。序中盤で大量に石を取ってしまうと(後半で)打てるところがほとんどなくなってしまい、パスや指定打ち(1箇所しか打てる所がない状態)になってしまいどうすることもできなくなってしまいます。
上図の場合、白は置ける場所が無く手詰まりだが、黒は取り放題。大逆転確実。
・中割り、開放度理論
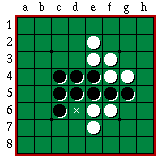
例えば図 1 の局面で白がd6に打つのが中割りです。この手によって白が返すのはe5の石で、このe5の石は周りを全て他の石によって囲まれています。このような「周りを全て他の石で囲まれている石のみを返す」手を中割りと呼んでいます。ちなみに英語では「Perfect Move」と呼びます。…裏を返せば「相手の中割りの手を消す」ことも重要。相手に中割りの手がなければ、相手はどこかに中割りではない手を打たなければならず、それはすなわち自分の打てる箇所が増えることになります。
(補足)「相手の打てる場所を増やさない」ことで優勢となるため、中割りは最大のチャンス。中割りでなくとも「なるべく内側、なるべく囲まれている少数の石」を狙うだけでも有利。”開放度理論”と呼ばれています。
・有利な形、不利な形
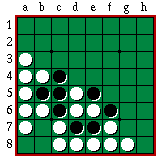
白、下辺の形をウィングと呼びます。一般に悪形です。
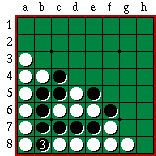
このように左下隅に置くことができても、空いたb8にあっさり割り込まれ下辺が全滅してしまう。
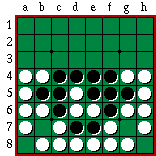
こちらは山と呼ばれる。この形は安定しており、一般に良形であると言われています。ウイングのように割り込まれる隙が生じにくい。
・辺への展開
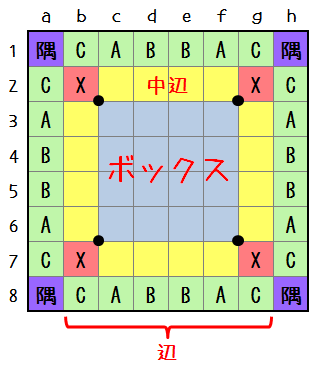
オセロ・リバーシの勝ち方、必勝法より
「迷ったらA打ち」と言われる。相手がCに置けば直ちに隅に飛び込めるからだ。
逆に、勝算なくCに打つべきではない。常に隅を狙われ続けてしまう。
いずれにせよ腕に自信が無いうちは辺への展開は後回しにし、中央付近で粘ることをオススメします。
まとめ
オセロ症候群は自覚が難しく、パートナーや友人が振り回されてしまう。自信の乏しさ、不安が根底にあると思われますので、まずは心にゆとりを持てるような工夫、生活の見直しから始めましょう。
オセロ(リバーシ)の世界は奥が深い。将棋や囲碁に比べてルール、盤面がシンプル故、AIも作りやすいみたい。(白:後攻が若干有利との説があります。が、まだ完全なる必勝パターンの答えは出ていない。)中級者になると「X打ち」「偶数奇数理論」などの戦術が活用されるのだが、私自身まだその域に達していない。修行あるのみだ!
以上。




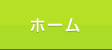
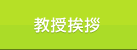
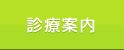


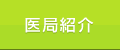
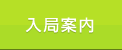



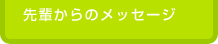
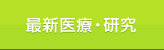




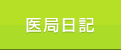
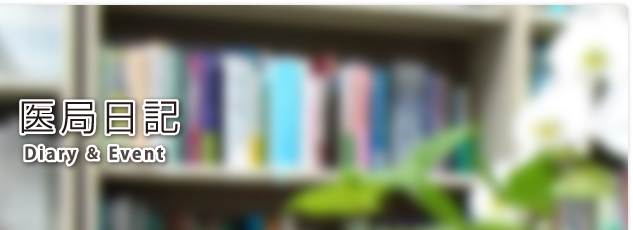
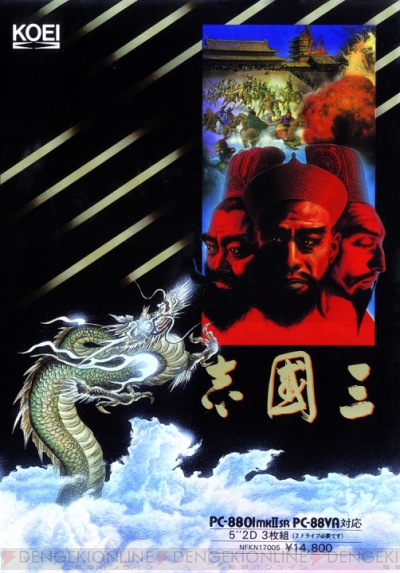
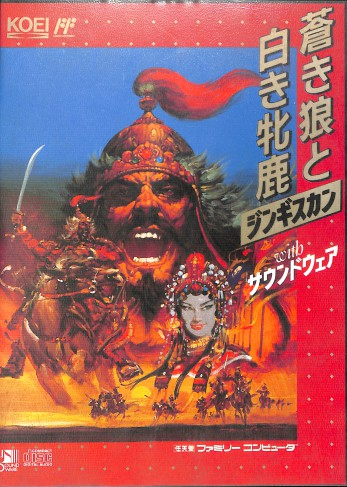



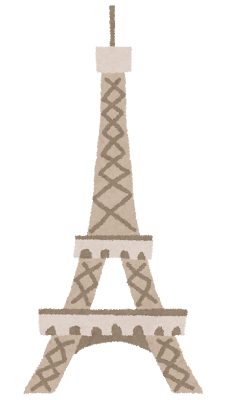
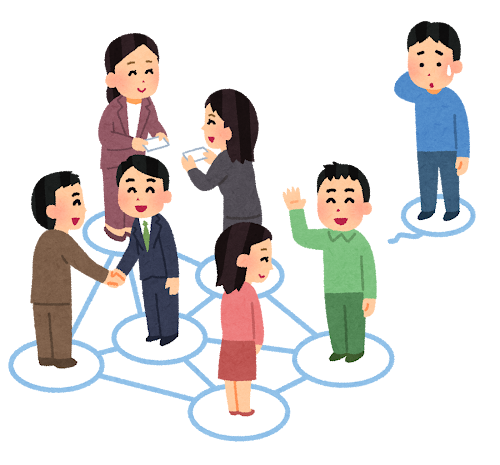

 (
(