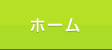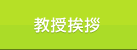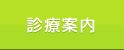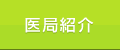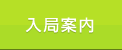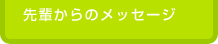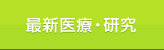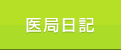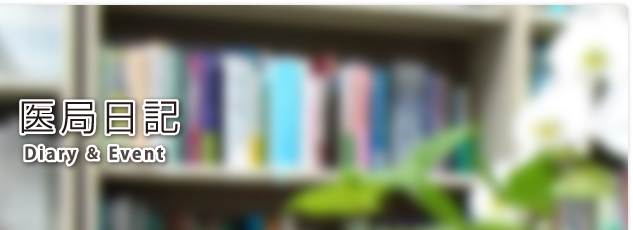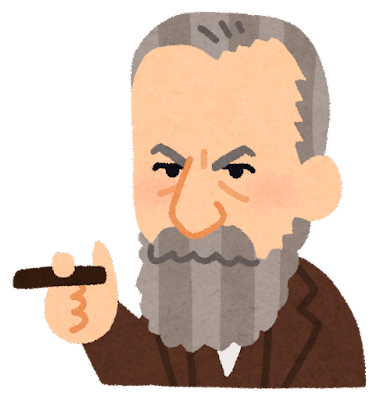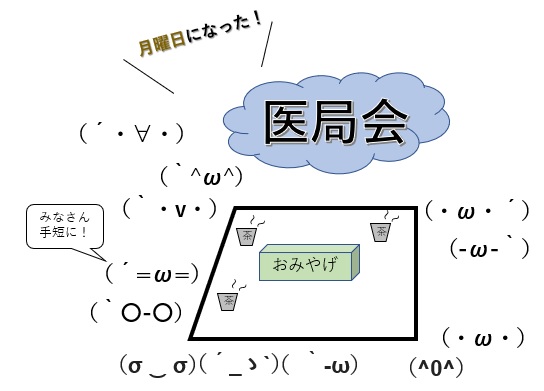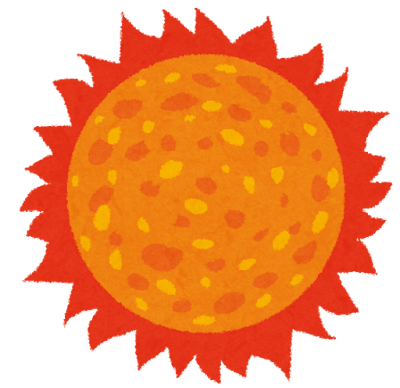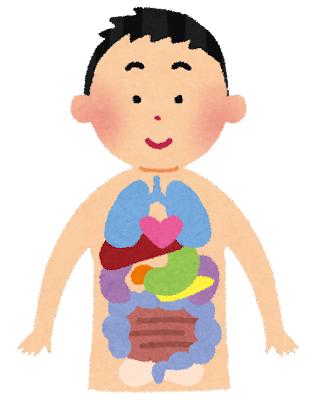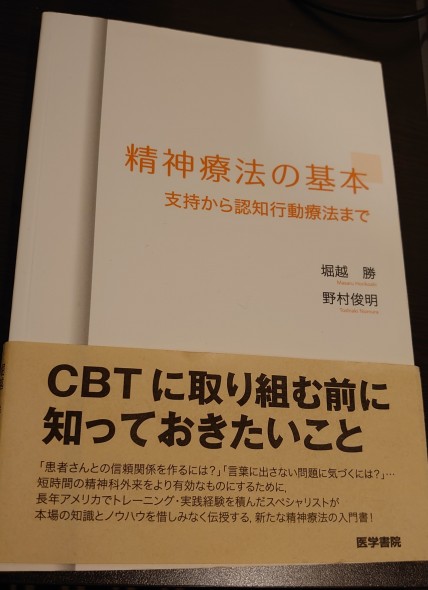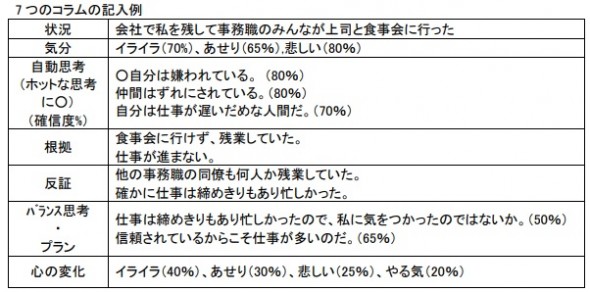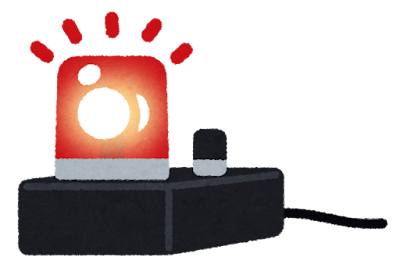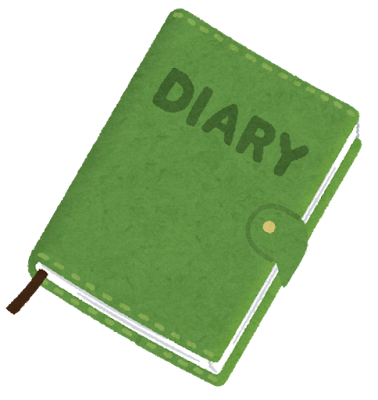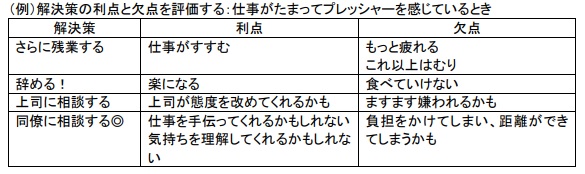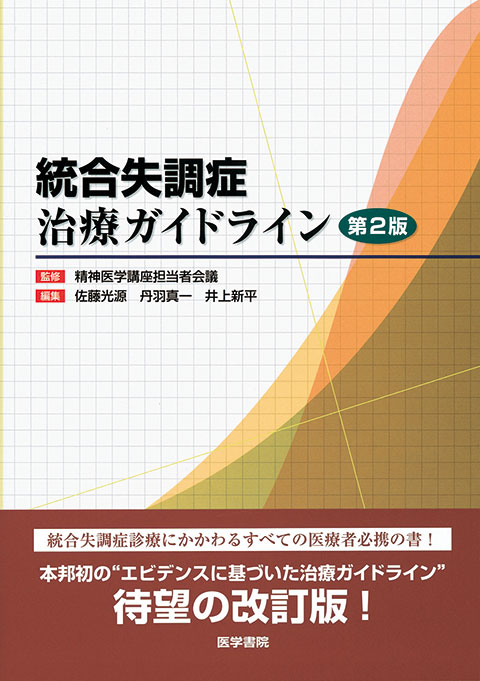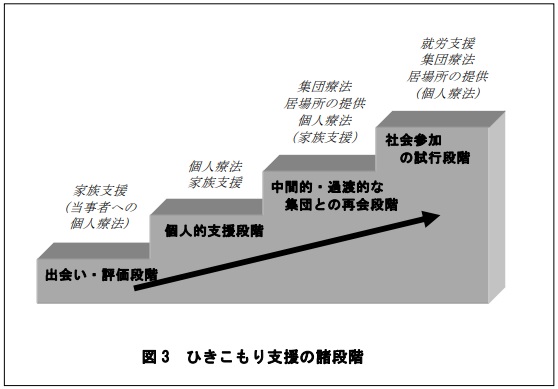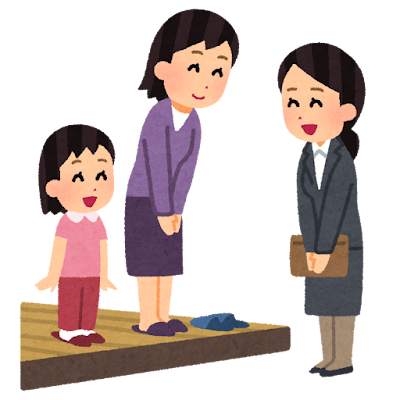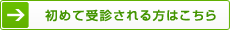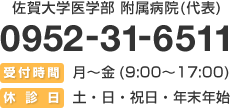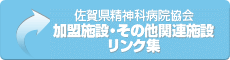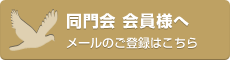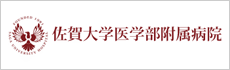ウェブセミナー(リモート勉強会)
(`・ω・)「皆さん、今日のお昼にwebセミナーやります!僕が発表します」
(`・ω・)「座長は、M病院のF先生!若手ながら活躍されています」
(・ω・)おお知ってます!私の研修医時代の上司でした
(`・ω・)「君のことも覚えていたよ!『よろしくお伝えください』と」
(・ω・)嬉しいッス!
~開幕前~
(`・ω・)「いやー緊張して昨日は眠れなかったよ!たった4時間」
(・ω・)教授にしては珍しい。普段は7時間でしたね
(`・ω・)「肩も痛くってね。コロナのワクチン打ったとこ」
(´・∀・)「奇遇です、僕もワクチンの痛みで眠れなかったです」
Σ(・ω・)もしや副作用?!
(`・ω・)「いや大したことないよ。登山後の肩の筋肉痛に比べれば」
(´・∀・)「そんなに激しいんですねー」
(`・ω・)「そろそろ時間。僕の部屋(教授室)で放送するんで、行ってくるねー」
(・ω・)よろしくお願いします!
(´=ω=)「zzz」
Σ(・ω・)医局長、もう寝てる
~放送開始~
(´〇ω〇)「皆さんこんにちは。それでは始めます。初めに門司先生のご紹介です」
(´〇ω〇)「昭和60年 九州大学医学部卒業、その後…んと、き、九州大学で助手をつとめたり、准教授…あ、えっと、佐賀大学の准教授となり、現職に至ります。と、とにかく多くの学会に所属し、視覚を所得されております」
(・ω・)…嚙んでる!噛んでる!
( `-ω)「教授の発表の座長って、若手にとっては滅茶苦茶緊張しますよね」
(`・ω・)「どうも!それでは始めます。うつ病に関する最新の知見で~」
(・ω・)(内容全部は載せられませんが、ポイントだけ紹介します)
(`・ω・)「うつ病になると『集中力や注意力の低下』『記憶力の低下』など、いわゆる”認知機能”が低下することがあります。」
(`・ω・)「分かりにくい症状ですが注意が必要です。再発率や、復職までの期間に影響を与えます。」
(`・ω・)「昔のうつ病治療は”症状を治す”が目標でしたが、現代では”リワーク(復職)”を目指すのが大事です。症状が治ってもこれまで通りの生活に復帰できない…というのは、患者さんにとっては辛いことなんです。」
(`・ω・)「基本は”ステップごとに、ゆっくり進めていく”です!日常生活のリズムを整え、短時間の慣らし勤務を経て、最終的に通常業務。いきなりフルタイムに復帰、はオススメできません」
※参考資料

うつ病の休職者を復職させる場合の注意点5つを弁護士が解説!
(`・ω・)「何はともあれ、うつ病の治療は”早めに気付き、早めに治療する”が大事です。発症から治療までの期間が短いほど、復職までの期間が短くなりますよ!」
~終了後~
(`・ω・)「お疲れ様!みんな観てくれてありがとう」
(・ω・)勉強になりました!
(`・ω・)「いやぁお腹空いた、お昼ご飯これから食べます」
Σ(・ω・)まだ食べてなかったんですね
(`・ω・)「ところで気付いたかい?発表スライドのTMSのとこ、座って治療受けてる人の写真」
(´・∀・)「あれ僕です」
Σ(・ω・)リエゾン医長だったんですか
(`・ω・)「いやぁ、患者さんに写真お願いするのも難しいから、身内で撮れば良いか、という。」
(`・ω・)「それにしてもwebでの講演って良いね!移動しなくても議論できるし、何より参加者数」
(`・ω・)「地方の勉強会って、参加を呼び掛けてもなかなか集まらないんですよ。大抵、平日の夜だし」
(`・ω・)「でもインターネットなら、同時に沢山の人に観てもらえる!良い時代になりましたね」
(・ω・)リモートワークとしても、今の時代にマッチしていると思います!
以上。