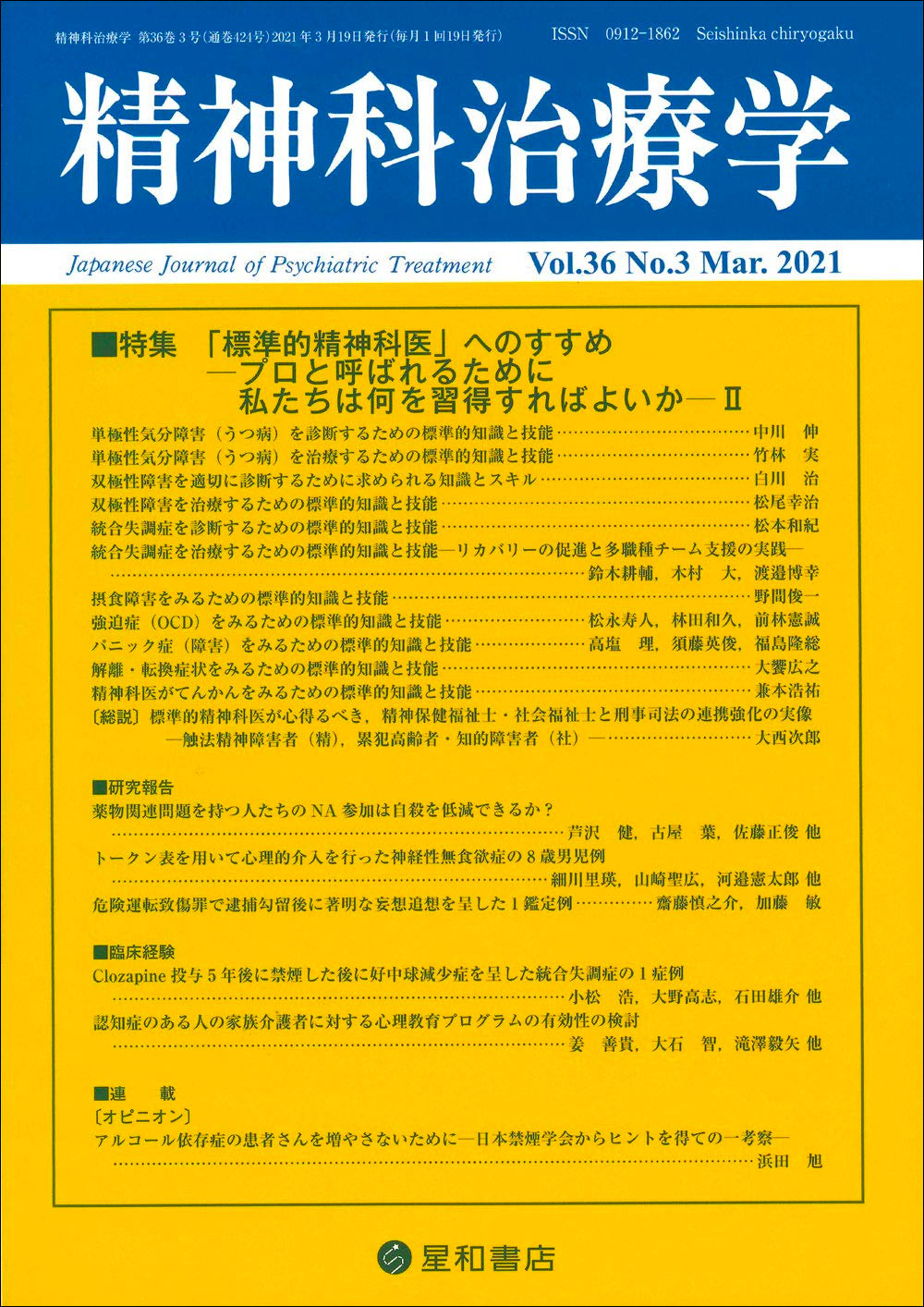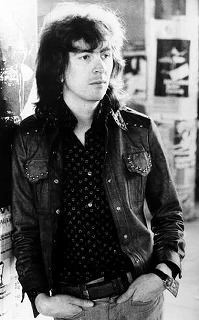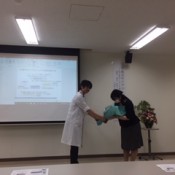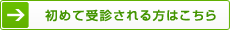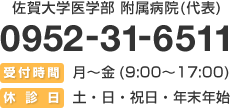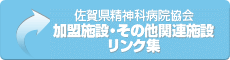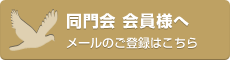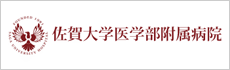~当直シフト決めは大変です~

(`〇-〇)國武医長「9月の連休の当直ですが、くじ引きで決めたいと思います」
(さぁ一人一枚、恨みっこ無しだ!取れ取れー)
「やったー当直無しだ」「ありゃー連休初日かー」ワイワイガヤガヤ
(´-ω-)溝口准教授「あの、私、この日は無理なんだけど…」
(σ‿ σ)永浜医員「”宅直”が当たっちゃいましたけど、私まだ新人なんですが…」
(`・ω・)門司教授「宅直の実態!いやぁー僕が九州大学に居た頃にひと騒動あってさー」
(`^ω^)野上助教「わはは、それは面白い」
(´-ω-)「えっと、あの」
(`〇-〇)「うーん、とするとこの日に入れる先生は…村川先生だけか」
(´・∀・)村川助教「(”当直なし”引いたのに)ええ…ま、まあできなくも無いですが…」
(´-ω-;)「いや本当にこの日無理なんで何とかしてください…」
( `-ω)某医員(…くじ引きにした意味が無いような)
(`〇-〇;)「(フリーズ中)」
(`〇-〇;)「も、もう一回シフト決め、考え直してきます」
大学病院という立場上、人数少ない科であろうが必ず毎日一人、当直に入らねばなりません。ベテランの先生は勿論、みなさん様々な用事(休日にも仕事あったり、勿論プライベートの用事だったり)があるので、シフト決めは大変です。
(・ω・)國武先生お疲れ様です!
~今年の日本精神神経学会、現地開催は中止!~

https://www.c-linkage.co.jp/jspn116/
日本精神神経学会 第116回学術総会 現地開催中止と開催方式に関するお知らせ
(`・ω・)「仙台で開催・オンライン配信の二本立ての予定だったんだけどね」
(`・ω・)「やっぱり現地開催は中止、となりました。仕方ないね」
~【精神科専攻医の皆さんへ】学会発表について~
https://www.jspn.or.jp/modules/newspe/index.php?content_id=60#02_08
新専門医制度 専門研修に関するQ&A
(´-ω-)「精神科専門医の申請においては、”学会発表の経験”が条件に含まれています」
(´-ω-)「『どの規模の学会発表』か?については、公式サイトに説明あります」
”学会ホームページのイベントカレンダーに掲載されているもののうち、「A群」「B群」のものが原則として対象となります。”
(´-ω-)「地方の小規模な発表会とかだと「C群」だったりしますので注意しましょう」
(`・ω・)「若者たち、どんどん学会発表してね!」
~新型コロナ、再流行?対策どうする~

(´・∀・)「別の病院では、”職員は半径30kmから離れてはならない”という対策が始まりました」
「何と!」「それは厳しい…」「うちはどうなるんだろう…」ガヤガヤ
(`・ω・;)「うちの病院の上層部も状況わかってはいるんだが、コロナ対策での赤字が無視できなくなってきているんだよ。対策を厳しくし過ぎると病院が潰れかねないという」
(`〇-〇;)「できるだけ外出や面会を控える、など出来る範囲でやるしかなさそうですね」
~痛みを考える会 開催のお知らせ~

(`・ν・)松島助教「毎年恒例の勉強会である”佐賀・痛みを考える会”、9月に開催決定しました。」
(`・ν・)「例年、整形外科、麻酔科、精神科、のスタッフが主に参加しています。今回は歯科口腔外科の先生も参加してくれるようです」
慢性疼痛をテーマとした勉強会です。医療従事者のみなさま、ぜひご参加ください(・ω・)
本日は関係者向けの連絡事項ばかりになってしまい恐縮です。
いやまあ、医局会ってのは本来そういうものなんですけどね。
何やかんやで毎回何かしら盛り上がるテーマが出てくる、愉快な医局です。
(・ω・)以上。




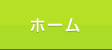
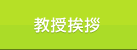
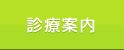


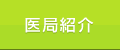
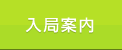



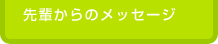
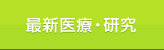




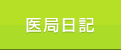
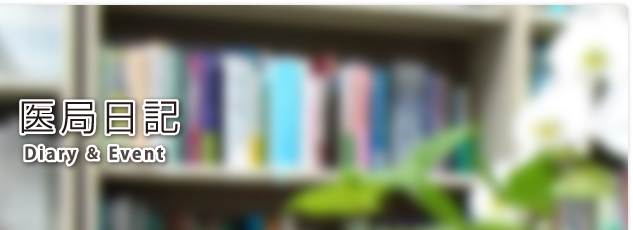





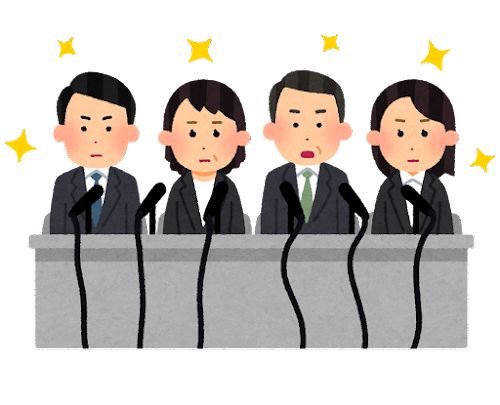



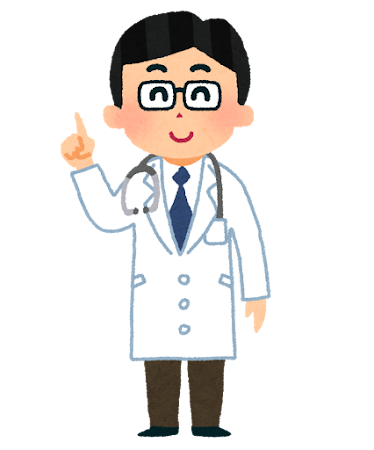
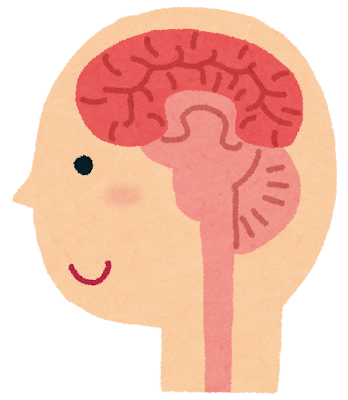
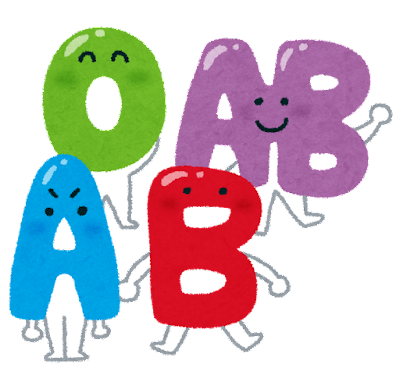


 (適切な画像が見つからなかった…怒らないで)
(適切な画像が見つからなかった…怒らないで)