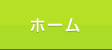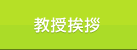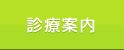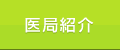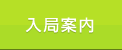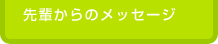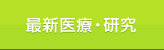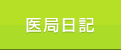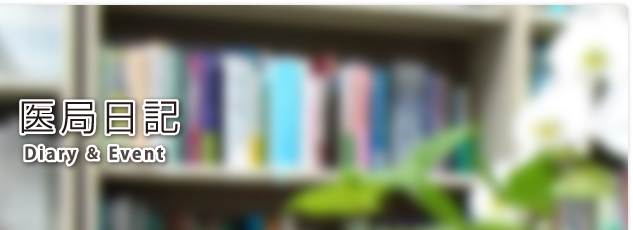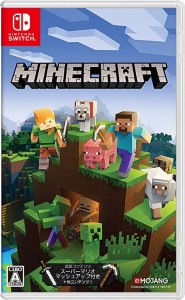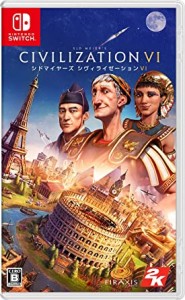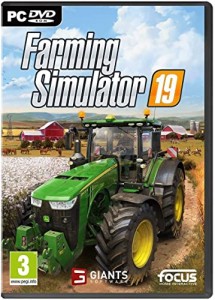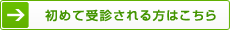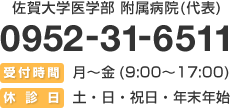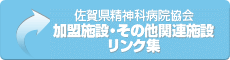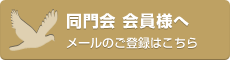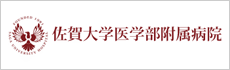時間を忘れて楽しめる、おまけに知識や教養が身につく、そんな素敵なゲームについて書いていく。
別に紹介とか、おすすめとか、そういう意図ではない。念のため。
MINECRAFT
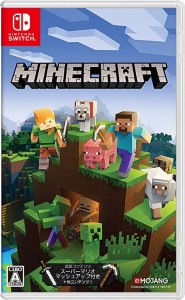
世界的に大ヒットした、モノ作り系アドベンチャー。
開発者はスウェーデン出身のプログラマー、マルクス・アレクセイ・パーション。
個人的に評価が高いポイントは”レッドストーン回路”と呼ばれるギミック。
何とこれ、電子工学系の基礎知識・理解が求められるレベル。
達人プレイヤーの中には、ゲームの中で電卓を作ってしまった強者まで。
その要素を除いても、採掘や建築、農業や畜産、資材の確保や運搬、保管、管理など
楽しみながら想像力、計画性が身につく。
KERBAL SPACE PROGRAM

宇宙開発シミュレーション。制作はメキシコのベンチャー企業、SQUAD。
デフォルメされた太陽系第三惑星を舞台に、ロケットや航空機を設計し宇宙開発を進めていく。
ざっくり言えば”宇宙版MINECRAFT”。その自由度と奥深さは本格的。
第一宇宙速度、推力、浮力、比推力、TWR、ΔV、近点、遠点、アポジキック、ホーマン遷移軌道、etc…
割と本気で宇宙科学、航空力学の基礎知識が身についてしまう。
(実際に学習教材として取り入れているところもあるらしい)
その分、かなり真面目に勉強する必要にも迫られる。
ちなみに私の場合、ゲームの攻略法を調べるつもりが、
気が付いたらJAXAのホームページで勉強してた。それくらい教養深いゲーム。
CIVILIZATIONシリーズ
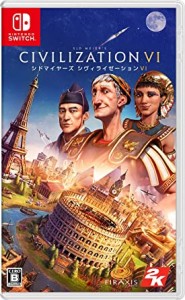
石器時代から宇宙開拓時代までを体験する、文明戦略シミュレーション。
カリスマゲームデザイナー、シド・マイヤーが開発。
次々と新作が出ており、2020年4月時点での最新作は6。ちなみに私は4を購入した。
4作目のオープニングテーマ曲”Baba Yetu”はグラミー賞を受賞した名曲。
科学、宗教、文化、世界遺産、偉人、経済、外交…遊びながら人類史が学べる。
面白い点として、実際の歴史では滅亡してしまった文明も平等に扱われているところ。
マヤ、インカ、アステカ、ズールー、シュメール、とか。
ゲームを極める頃には人文科学基礎レベルの教養が身についていることだろう。
問題点としては、中毒性が高すぎて依存症レベルになる人が続出したこと。
私もこれが原因で学業に多大な支障が出た。(現在は何とか社会復帰できたが)
名作であることは間違いないが、絶対におすすめできないゲームだ。
Farming Simulatorシリーズ
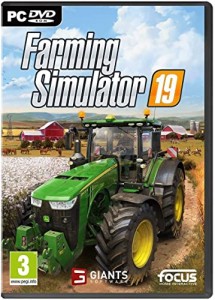
読んで字のごとく。農業シミュレーション。
すみません、実は未だ私はプレイしていない。
ただ、私の先輩が
「早く仕事を終えて、農作業に戻らねば!」
とか言い放った姿が衝撃的だったので…。
そんなに面白いのだろうか。やってみたいが、まだそこまで時間的余裕が無い。
以上。