5月16日金曜日
18:30~大学で説明会があります。
19:00~談話会 場所は未定です。
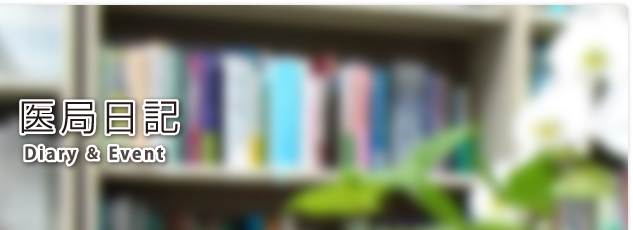
5月16日金曜日
18:30~大学で説明会があります。
19:00~談話会 場所は未定です。
4月18日金曜日の19:00より談話会があります。場所は未定です。
Baron-Cohen S, Johnson D, Asher J, Wheelwright S, Fisher SE, Gregersen PK, Allison C. Is synaesthesia more common in autism?
Mol Autism. 2013 Nov 20;4(1):40. doi: 10.1186/2040-2392-4-40.
共感覚とは、ある感覚器への刺激によって本来知覚される感覚だけでなく他の種類の感覚が知覚される現象である。例えば文字や数字が色に見えたり、音に色や形が見えたりする。共感覚が起こるメカニズムとして、様々な仮説があるが、通常はみられないような神経細胞の結びつきがみられると言われている。自閉症もある限られた部分で神経細胞の結びつきが強いことが言われている。
この文献では、自閉症スペクトラムの人とコントロール群で、共感覚を持つ人の割合を調査した結果、コントロール群(約7.2%)に比較して約3倍(18.9%)高いことがわかった。他の文献においても、共感覚は遺伝性がある可能性があることを示唆した文献や、画像(MRI、fMRIなど)を組み合わせての調査など様々な研究報告がされている。共感覚は第3者が確認することができないため、なかなか原因の解明は困難だと思われるが、非常に神秘的で面白い現象であり、とても興味深く感じる。
An fMRI-Based Neurologic Signature of Physical Pain
Wager TD et al. N Engl J Med. 2013 Apr 11; 368
「身体的疼痛の機能的磁気共鳴画像法(fMRI)による神経標識」
【要約】
【背景】
疼痛は自己評価に基づいて行われるのが一般的だが、それのみでは診断と治療の妨げとなることがある。fMRI痛みの客観的な評価を同定するものとして有望視されているが、感度および特異度を有する脳の測定はこれまで特定されていなかった。
【方法】
4試験(被験者は合計114名)を行い、各個人が感じる痛みの強さをfMRIに基づいて評価することを開発した。
(試験1)
熱誘起疼痛による脳領域横断的なfMRI活動性パターン(“神経標識”)について、機械学習によって分析した。このパターンには視床、後方・前方島皮質、二次体性感覚皮質、背前方帯状皮質、中脳中心灰白質や他の領域が含まれていた。
(試験2)
別の被験者で身体的疼痛と温感に対する“神経標識”の感度と特異度を分析した。
(試験3)
身体的痛と同領域の脳の活性を促す社会的疼痛について、“神経標識”を分析した。
(試験4)
鎮痛剤であるレミフェンタニルに対する“神経標識”の反応性について評価した。
【結果】
(試験1)
“神経標識”は有痛性熱刺激と無痛性熱刺激、疼痛の予期、疼痛の想起との識別について、感度、特異度は94%以上を示した。
(試験2)
“神経標識”による有痛性熱刺激と非有痛性熱刺激の識別の感度・特異度は93%以上だった。
(試験3)
身体的疼痛と社会的な疼痛の識別85%の感度と78%の特異度だった。またどちらの状況がより強い痛みか識別する感度と特異度は95%だった。
(試験4)
レミフェンタニルに対する“神経標識”の反応の強さは投与により明らかに減少した。
【結論】
健常への熱により誘発された疼痛をfMRIで評価することは可能である。この“神経標識”が臨床的な痛みを予測するか評価するには、更なる研究が必要である。
(コメント)
痛みの評価は、患者さん本人の自己評価に基づいて行われていますが、客観的な指標がなく、過小評価されることもあるため、今後、各個人において客観的な指標が補助的に使われるようになれば、痛みの評価、治療に役立つと思われます。また、疼痛性障害や繊維筋痛症などの原因が解明されてない慢性疼痛の機序解明につながる可能性があると思いました。
Behavior and Severe Neuropsychiatric Disorder Following Glucocorticoid Therapy in Primary Care
Laurence Fardet et al.: Am J Psychiatry 2012;169:491-497.
ステロイドの全身投与を受けた患者に自殺行動や重篤な精神障害が多いことはあまり知られていない。著者らは、イギリスのTHIN(健康づくりネットワーク)をのデータベースを利用し、プライマリケアにおいて、ステロイドの傾向内服をしている患者の、精神疾患発生のリスクを検討た。対象は、約3万7千人のステロイド投与患者で、その約4倍の非投与患者が対照にされた。
ステロイド治療を受けた患者では、非投与患者に比べて各精神障害の発症リスクが、うつ状態で約2倍、そう状態・せん妄状態・混乱・見当識障害が約4-5倍、自殺・自殺企図が約7倍であった。また、女性ではうつ状態、パニック障害、自殺企図が男性に比べて多く、年齢別にみると若年でパニック、自殺企図が多く、高齢でせん妄、そう状態が多くなることが分かった。
精神疾患の既往があると、ステロイド治療後に同じ精神障害が惹起されやすいことがわかった。
ステロイド治療による精神障害に関して、プライマリケア医は患者および家族に十分な説明を行い、注意深い観察をすることが重要である。
Ahmari SE, Spellman T, Douglass NL, Kheirbek MA, Simpson HB, Deisseroth K, Gordon JA, Hen R.
Repeated cortico-striatal stimulation generates persistent OCD-like behavior.
Science. 2013 Jun 7;340(6137):1234-9.
強迫性障害の病態に、皮質-線条体-視床-皮質(CSTC)回路の機能不全が関与するとされるが、因果関係はまだ充分に明らかになっていない。今回Ahmariらは、光遺伝学的手法(optogenetics)を用いて、強迫性障害患者で観察されるCSTC回路の過剰な活性化をマウスにおいて再現しようと試みた。マウスの眼窩前頭皮質(Orbitofrontal cortex: OFC)-腹内側線条体(ventromedial striatum : VMS)経路を短時間刺激しても繰り返し行動を惹起しなかったが、数日間に渡る繰り返し刺激はマウスにおける強迫行為のモデルである毛繕い行動を徐々に増加させた。一旦増加した毛繕い行動は、刺激中止後も2週間以上持続した。毛繕い行動の増加は、光刺激による後シナプスVMS細胞の発火と時間的に密に関連した。毛繕い行動および発火頻度の増加について、強迫性障害の治療に有効なフルオキセチン投与によりいずれも抑制された。OFC-VMS経路の短時間でも連続した過活動によって持続した強迫行為が生じる可能性がある。
Popovic D. et al.: Polarity index of pharmacological agents used for maintenance treatment of bipolar disorder. Eur Neuropsychopharmacol (2012) 22: 339-346.
半数以上の双極性障害(BD)患者が,うつまたは躁のいずれかの極に優位に再燃すると報告されている。本研究では,BDの維持療法における各薬剤の特徴を,polarity index(PI)によって評価することを試みた。PIは薬物の相対的な抗躁,抗うつ予防効果を示す新しい指標である。BD維持療法において,気分安定薬単独,抗精神病薬単独または気分安定薬併用の,24週以上にわたる再発予防効果を調べた二重盲検化プラセボ対照RCTの結果を用いて,うつの予防効果と躁の予防効果のNNT比によりPIを算出した。PIが1以上の場合,相対的に抗躁予防効果が抗うつ予防効果を上回ることを示す。各薬剤のPIはリスペリドン12.09,アリピプラゾール4.38,ジプラシドン3.91,オランザピン2.98,リチウム1.39,クエチアピン1.14,ラモトリギン0.40であった。バルプロ酸とオキシカルバマゼピンは維持療法の治験そのものを失敗したため,信頼できる結果が得られなかった。PIはBDにおける薬物の抗うつ/抗躁効果比を数値化しているため,維持療法における選択基準の一つとなりうる。